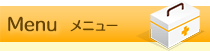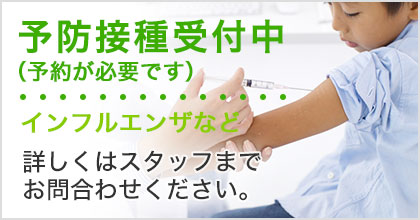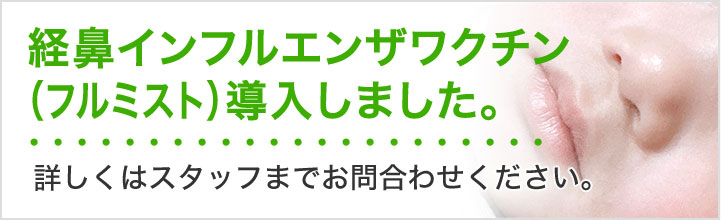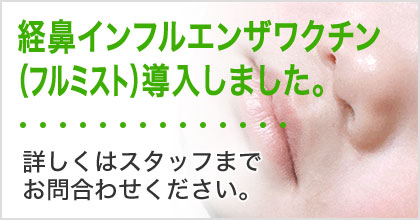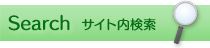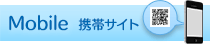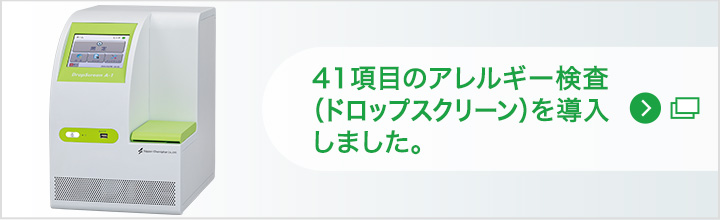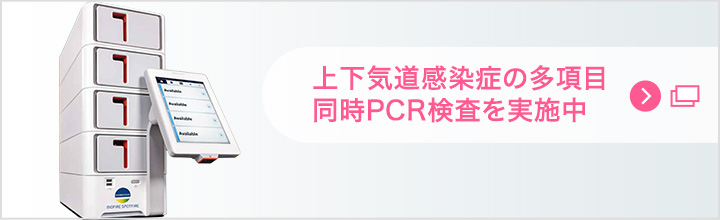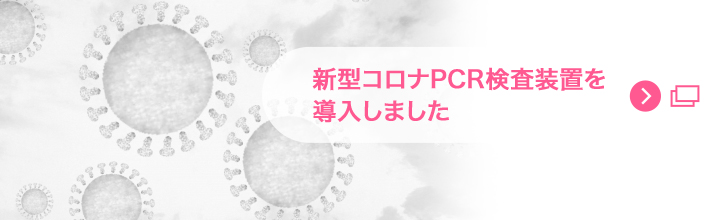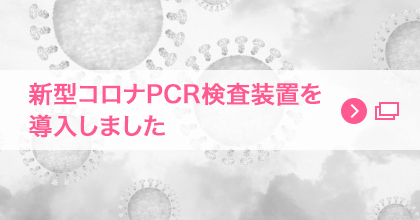10年ほど前、私は日本耳科学会の元会長であり、京都大学耳鼻咽喉科学教室の大先輩でもある山本悦生先生に、ひとつの質問を投げかけました。
「鼓膜のバネの復元力が、中耳調圧の原動力ではないのですか?」
先生は一瞬黙り、そして静かにこう答えました。
「それは関係していると思う。しかし中耳調圧に関しては、何の証拠もないのよ。だから、何を主張してもいいのよ。」
私はその言葉に愕然としました。耳科学という分野が、100年近くの間、「中耳の圧力調整」という基本的な現象について科学的根拠を持たず、物理学的検証もなされてこなかったという事実が、そこにあったからです。
では、この「中耳調圧」とは何か。私たちが飛行機に乗って離陸し、高度が上がったときに耳が詰まる。つばを飲むと「ポン」と音がして、耳が抜ける――この日常的な現象こそが、中耳の調圧(圧力平衡)です。
私の問いかけは、それを物理学の視点で説明できるのではないか、というものでした。
そして、その問いに「科学」が明確に答えを出しました。
私は、耳管の開閉タイミングを制御した状態下での中耳の圧力変化を、時系列で計測・解析し、その挙動が「指数関数的減衰」であることを突き止めました。
これは、物理学で言うRC回路(抵抗×容量)や、マクスウェルモデル(弾性×粘性)の世界で知られるエネルギー放出の基本パターンです。
つまり、中耳調圧は完全に物理法則に従った自然現象なのです。
加えて、鼓膜にSteri-Stripを貼ることで弾性(剛性)を高めると、調圧速度が著しく速くなることも確認しました。
この事実は、中耳の圧力調整が「鼓膜のバネ」と「耳管抵抗」によって支配されていることを、明確に示しています。
ところが、この物理現象に対して、耳科学の世界は10年間『沈黙』を続けています。
私が学会で発表しても、反論も質問もない。論文を投稿しても、初期審査で門前払い。再現性があり、データも揃っているにもかかわらず、検証すら試みられないのです。
なぜか? 答えは明白です。
このモデルを受け入れてしまえば、これまで耳科学が100年以上「中耳陰圧が悪い」「鼓膜のへこみは陰圧が大きい」としてきた説明の多くが、根本的に誤りであったと認めることになってしまうからです。
科学とは、証拠によって定説を修正する営みです。
それを拒否したとき、学問は閉じた体系になり、やがて“宗教”のようなものになってしまいます。
ティンパノメトリーのピーク圧変化は外気圧変化をそのまま表示しており、それは中耳とティンパノメトリーで全ての人が、外気圧変化から算出される高度計になるほど正確です。ピーク圧は中耳相対圧を示すものではありません。その解釈でも、耳科学は科学的整合性を欠いたものになってしまいました。
私の10年越しの問いかけに、科学は明確な答えを出しました。
あとは、それを耳科学が受け入れる勇気を持てるかどうか――。
そして耳科学は「科学からの逃避」から抜け出し、真の科学として再構築できるかどうか。
それが、耳科学の医学としての未来に問われているのです。
私は耳科学を批判しているのではありません。
私が繰り返し訴えているのは、現在の耳科学が“知らず知らずのうちに”多数の調圧不良耳を生み出し、その結果として本来防げるはずの中耳疾患を見過ごしている、という事実です。
つまり、現在の耳鼻科診断は科学ではなく、アンケートのような基準の積み重ねにとどまっています。
私が求めているのは、耳科学を否定することではなく、物理学的な数値とエビデンスを導入した“真の科学”としての耳科学の再構築なのです。
滲出性中耳炎の子どもの耳は、治ったように見えても実際には鼓膜のバネがほとんど劣化しています。
私の調査では、一度でも滲出性中耳炎を経験した耳のほぼ全例で鼓膜バネが弱っているのです。
そのため、学会報告にもあるように84%の子どもは耳管が通っていても耳の圧調整ができない。
つまり、耳のトラブルの本当の原因は「耳管」ではなく「鼓膜の劣化」なのです。
にもかかわらず、ガイドラインには「鼓膜の弾性が失われても問題ない」と書かれている。
これは、医師が病気を放置することを推奨しているに等しく、極めて危険です。
本当に守るべきは「耳管」ではなく「鼓膜のバネ」なのです。

 058-371-7650
058-371-7650 〒504-0803 各務原市蘇原東門町2丁目78
〒504-0803 各務原市蘇原東門町2丁目78